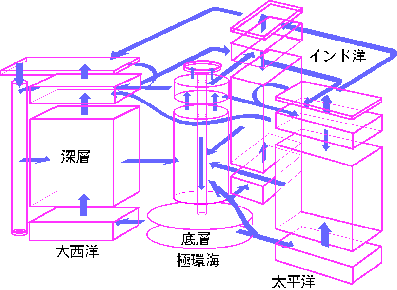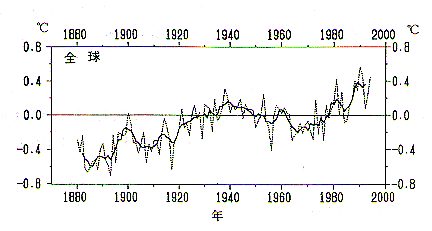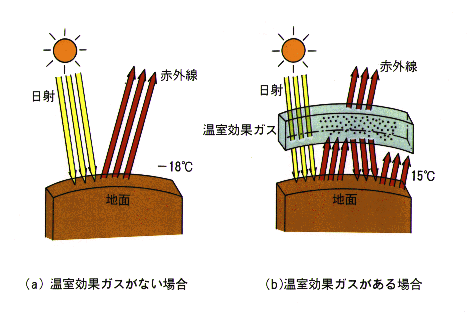気候とは「大気と海洋から成る熱機関である」とするならば、気候という熱機関を「大気」の部分と「海洋」の部分に分けて考えるのがひとつのやり方だ。実際、気候システム研究センターで用いられている方法もこれである。大気という熱機関の動力学の研究は「天気予報」という名前でわれわれにはお馴染みである。その目的とするところは、「太陽からの熱+海洋表面の温度」を与えた時に大気がどのように運動し、どのように温度が変化するかという事を知る事である。つまり、海洋という熱源と太陽という熱源、2つの熱源と熱のやり取りをしている熱機関として「大気」を扱うのが天気予報と言うわけだ。
気候とは「大気と海洋から成る熱機関である」とするならば、気候という熱機関を「大気」の部分と「海洋」の部分に分けて考えるのがひとつのやり方だ。実際、気候システム研究センターで用いられている方法もこれである。大気という熱機関の動力学の研究は「天気予報」という名前でわれわれにはお馴染みである。その目的とするところは、「太陽からの熱+海洋表面の温度」を与えた時に大気がどのように運動し、どのように温度が変化するかという事を知る事である。つまり、海洋という熱源と太陽という熱源、2つの熱源と熱のやり取りをしている熱機関として「大気」を扱うのが天気予報と言うわけだ。